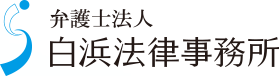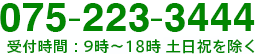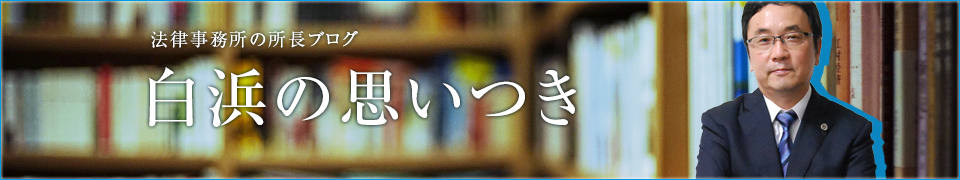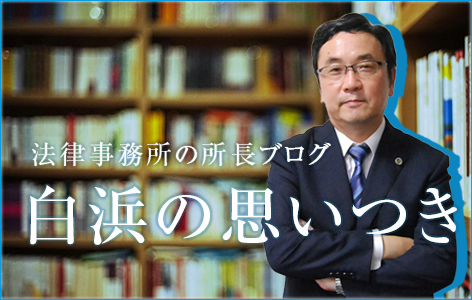地方の悲哀編
私が放浪記を会報に載せて欲しい訳
裁判所は「慣行」や「先例」を重視する世界のようだ。しかし、この「慣行」や「先例」は、ややもすると一般社会の常識からずれていることがある。そして、そのことは内部の人間にはわからないことも多い。弁護士は、在野法曹として、この妙な「慣行」を正す社会的使命があると思うのだが、その地方の弁護士会に所属していない弁護士には、問題を指摘する手段が事実上与えられていない。その点、弁護士会報は、各地の弁護士会に送られるから、これを書くことで、「慣行」改善の何かのきっかけになるやも知れないと思って、期待するところがある (※1)。
さて、前回は、東京や仙台などの権威ある裁判所での体験を書いたが、地方(但し、大都市に対する意味での)の事件でも、困ったり、苦労したりすることがある。以下は、その体験談の一部である(前回お断りしたように、この話も、あくまでも主観的なものである。)。
セルフサービスです(来たれよ、さらば与えられん その1)
再び仙台地裁でのお話。とは言っても、本庁ではなく、支部である。
仙台地裁のとある支部の事件で記録謄写をするよう事務局に指示したところ、事務員から「謄写はできないそうです。」とのこと。びっくりして詳しくきいてみると、「支部では、記録謄写をするところがないから、弁護士自ら謄写に来るか、事務員を派遣するか、あるいは、知り合いの弁護士に依頼して謄写してもらうかして欲しい。謄本申請をするのであれば、謄本としてなら交付する。」 と言われたというのである(※2)。これでは、私か事務員のいずれかが、飛行機に乗って東北まで出張して謄写をせねばならなくなる。費用や時間を考えれば、まさにとんでもない取り扱いである(なお、私が謄写しようとしたものは、謄本の交付ができないものであった。)。結局、次回期日に、早起きして開廷一時間前に出頭し、私自らコピーさせていただいた。なお、仙台弁護士会に、この問題を検討していただくようお願いしたところ、担当の庶務委員会委員長ご自身も、支部事件の記録謄写をどうやっているのかご存じないとのことであった。
独り言・・・「知り合いの弁護士などもいるはずがないし、当該事件に関係のない弁護士に記録謄写を依頼することは、弁護士の守秘義務やプライバシー保護の関係でも大いに問題がある。ただ、弁護士ならまだ対処の方法があるが、(もっとも、弁護士としても、支部まで事務員を派遣しているとすると、その費用をクライアントに負担させているのだろうが、仮にそのような扱いがなされているとすれば、疑問が残る。)、本人訴訟など一般市民が謄写をしようとした場合のことを考えると、果たしてそのままでよいのか、大いに疑問である。民事保全法や新しい民事訴訟法が、遠方から裁判所を利用する者の便宜を図っていることと(管轄区域外供託の許可や書面による準備手続など)、この謄写の扱いとは矛盾しているようにも思われる。」
支部とはなっていますが、人はいません。
これも私が独立開業する前の話。旭川地裁留萌支部に動産仮差押の執行を申し立てたところ、本庁の執行官から電話があった。「せっかく申し立てていただいたのですが、留萌支部には、常駐の執行官がいません。二週間おきに留萌の事件は処理しているのですが、今度ゆくときには、先生の仮差押決定は期間経過で失効してしまいますので、できれば取り下げてもらって、今度、私がゆくときに執行できるよう、出し直してもらえませんか。」とのこと(※3)。「そんなもん聞いてないよ!」と言いたいところだったが、泣く子と執行官には逆らえないので、取り下げて再度申し立てし直した。ちょっと日和見かも知れないが、動産仮差押は執行官と打ち合わせをしてからやるべしという鉄則を忘れていたからやむを得ないと思った次第である。
独り言・・・「執行官が常駐していないということは、結局は、内部の事務処理上の問題であって、外部からはわからないことである。このような内部処理をしているのなら、少なくとも弁護士便覧ぐらいには指摘があってもおかしくない。いずれにしても、支部に人材を常駐させることができないという裁判所の内情と過疎問題がリンクした難しい問題のように思う。」
最寄りの駅はありません。
鹿児島地裁知覧支部では、最寄りの駅がなく、鹿児島市内からバスでゆくしか交通手段がない(※4)。それも一時間程ゆられてゆくことになる。知覧への移送申立があったとき、この不便さを知って、相手方弁護士と協議し、京都在住の証人を京都で調べてから移送することで話をつけたところ(鹿児島の弁護士にとってもあまりゆきたくない支部のようであった。)、裁判所が、これを無視して移送決定をしてしまったことがあった。このときは、大いに怒って裁判官に抗議した記憶がある(書記官にはこの合意を伝えてあったのだが、裁判官には伝わっていなかったとのことだった。)。でも、知覧に実際にいってみると、ちょっとした高原にあって、隠れた観光名所でもあり、なかなかよいところではあった。
また、確かもう廃止されたと思うのだが、岡山の美作簡裁にいったときは、中国自動車道を高速バスにゆられていった記憶がある。最寄りの駅はあるのだが、バスを使った方が便利だし速かったのである。この簡裁は、法廷の真ん中にだるまストーブがおいてあって(確か、法廷の床は土間に近いものだったような気がする)、ほのぼのとした雰囲気があった。
ついでだが、先日、新潟地裁高田支部への移送申立があり、調べてみたところ、富山から特急で一時間以上乗って、更に急行に乗り換えて三〇分以上かかるということがわかり(上越や長野新幹線を使っても、これより早く着くことはできない場所である)、京都から最も遠い裁判所の一つであることが判明した。幸い、相手方に代理人がついており、しかも、富山の弁護士だったので、早々に取り下げて管轄合意をしてもらって、再度富山地裁に提訴し直した。新民訴で採用された「合意による移送」の制度に大いに期待するエピソードの一つである。
郵送は受けつけません(来たれよ、さらば与えられん その2)
今回のテーマとは離れるのだが、東京地裁のお話を補足したい。
東京地裁では、保全手続に弁護士の面談を要求している。窓際にずらりと並んだ保全部の裁判官席の前にはこれまたずらりと椅子が置いてあり、この椅子に座って、(裁判官の机を境にして)弁護士が面談することになっている。実際にいってみると、心なしか、検察官修習時代の取調を思い出す気分がした。このような弁護士面談を行っているのには、非弁防止の意味があるとのことらしいが、どれだけの効果があるのかは、疑わしいように思う。ただ、まあ、形式的ではあるが、非弁防止という点ではこの取扱には一定納得できる側面もあるが、理解しがたいのは、供託書の取扱である。管轄区域外の供託という利用者の便宜を図った制度があり、法務局も、この趣旨を尊重して許可書がなくても供託を認めてくれる取扱となっているのだが、東京地裁は、この供託書を裁判所まで持参せよというのである。これでは、保全手続の際には、東京に二度も出向かなくてはならないこととなり、事務所所在地で供託を認めた趣旨が完全に没却されてしまう。東京地裁の言い分では、供託書は金銭と同じだし、紛失したりした場合に責任が持てないなどというのだが、それは、内部の事務処理上の都合に過ぎない。実際、このような取扱は、東京地裁やその影響下にある裁判所で行われているだけで、ほとんどの裁判所は郵送を認めている。なお、東京や大阪、横浜などの裁判所を除けば、弁護士面談は必ずしも要求されないようになっているのが普通である。つまり、東京の弁護士は、地方まで出張しなくても保全決定を得られるのだが、地方の弁護士が東京で保全決定を得ようとすると、二度も東京にゆかねばならなくなる。民事保全法や新民事訴訟法が遠方の利用者に配慮しているのは、東京などの都市部に居住している者が地方の裁判所を利用する場合だけへの配慮だけではないと思うのだが、いかがだろう。いずれにしても、この問題は、地方に居住する者の特殊な問題に過ぎないから、東京での一審三者協議(裁判所、検察庁、弁護士会)の問題とならない。この京都の地で遠吠えを挙げるしか方法がないように思うのである。
——————————————————————————–
※1
出張で初めて訪れる裁判所では、弁護士でも、その地方独特の慣行に戸惑うことがある。ただ、裁判所に不慣れという点では、一般市民と似た感覚なのかも知れない。このように考えると、私が京都以外の裁判所に対して抱いた疑問は、一般市民の感覚に多少近いものがあるのかもしれない。
※2
このような扱いは、仙台高裁管内では一般的なようである。山形地裁鶴岡支部でも郵送による謄写依頼はできないとのことである。京都の場合も、支部事件は協同組合では謄写できない扱いとなっているが、実際には書記官さんが謄写してくれているらしい。やはり関西の裁判所は東北の裁判所よりやさしいということだろうか。
なお、佐賀県弁護士会では、謄写担当者が支部に出張して謄写しているとのこと。弁護士会の規模(確か三〇名程だと思うが)から考えるとすごいことである。感心した。福岡でも、支部を掛け持ちして謄写している謄写官がいるとのこと。また、書記官さんが謄写してくれることもあるらしい。この取扱に関しては、九州の法曹関係者の方が、関西の関係者よりも利用者にやさしい取扱をしているように思える。
※3
支部に裁判官が常駐していないところは多く、そのことはたいていの弁護士は知っていると思うが、盲点は執行官である。過疎地域では、執行場所まで遠いことも多いわりに、事件数は少ないから、執行官は大変なのである。大津地裁でも、執行官は、湖東地区と湖西地区を分けて、交代で処理していると聞いた。
※4
裁判所は、お城のそばにあることが多い。広島地裁は鯉城のそば、熊本地裁も熊本城のそば、彦根支部は彦根城のそばといった具合である。そして、だいたいは、最寄りの駅はJRの駅ということになるが、福岡地裁柳川支部は西鉄の駅の方が近いなど例外もある。なお、ついでだが、支部を含めて、裁判所には同じ名前のところはないと思うので、暇な人は確認してみてほしい(JRの駅や市町村の市の名前も同一のものはないらしい)。
——————————————————————————–
(注) 本稿は、すでに、京都弁護士会会報(98年1月号)に掲載されたものです。また、京都弁護士会ホームページに於いても再掲されています。原稿に書かれた内容は、白浜が経験した、当時のものであるということを、お断りいたします。
著 白浜徹朗