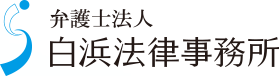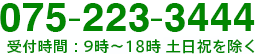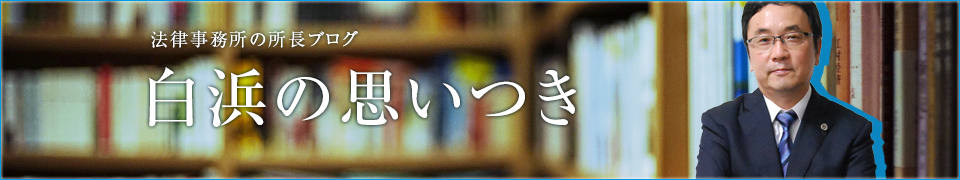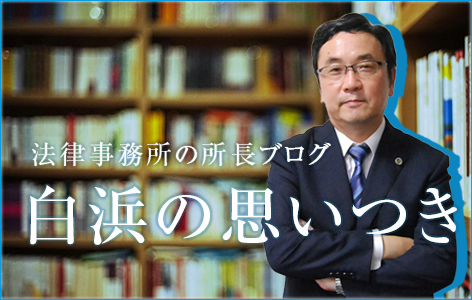2010/01/01
2010 初春号 vol.6 白浜法律事務所報
これまで弁護士事務所は、裁判所のそばで開業し、ご相談には裁判所近くの事務所まで足を運んでいただくことが一般的でした。結果的に、弁護士は市民のみなさんから縁遠い存在となり、弁護士の過疎偏在という問題にもつながっていたように思います。
特に乙訓地区は、約15万人もの人口を抱える地域でありながら、弁護士会の相談センターもなく、弁護士への相談は、京都市内または大阪市内まで出向いていただくほかない状況が続いておりました。
私たちは、このような状況を少しでも改善し、弁護士がもっと身近な存在になればと考え、長岡京の地に支所を開設することといたしました。
これからも市民のみなさんのよき相談者として、問題解決のお手伝いをさせていただきます。
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
新しいスタートです
弁護士 白浜徹朗
昨年は、長岡京に支所を開設することができました。私は、弁護士が裁判所のそばに事務所を構えてお客様には事務所まで来てもらって仕事をするというスタイルには昔から疑問を持っておりましたので、長年の夢がようやく実現できたという感じです。長岡京事務所は、昨年12月15日に開所式をさせていただき、翌16日から執務を開始しています。乙訓地区は、人口約15万人を抱える地域ですから、この地域の皆様が弁護士という職業に対して不快感を抱かれるようなことがないよう慎重な対応が求められるとの自覚の下に、長岡京事務所では本所にも増してより丁寧な仕事をしてゆこうと考えております。
同事務所に所長である私と一緒に赴任してもらう青野理俊(まさとし)弁護士は、昨年12月18日に弁護士になったばかりの弱冠26歳の新進気鋭の弁護士です。青野弁護士は、私が育成に関わることになる9人目の弁護士ということになりました。同弁護士は、京大で居合道部の主将を務めていたということで、登録初日から仕事に取りかかるなど、職務に真剣に取り組んでもらっています。長岡京事務所同様、青野弁護士にも、暖かいご指導ご鞭撻を賜りたくお願い申し上げます。
ごあいさつ
弁護士 青野 理俊
初めまして。新人弁護士の青野と申します。
私は、この度、弁護士法人白浜法律事務所の長岡京事務所におきまして、弁護士としてのスタートを切ることになりました。皆様どうぞ宜しくお願い致します。
私は、神戸で生まれ育ちましたが、京都大学法学部に入学とともに京都に移り住み、ロースクールも京都大学、司法修習も京都配属でしたので、26歳となる現在、かれこれ8年間京都に住み続けております。そのため京都は第2の故郷となっておりまして、是非縁のある京都を支える弁護士になりたいと思い、京都で弁護士登録を致しました。
私の特技は、大学入学してから今も続けている居合道です。居合道とは、袴と刀を身につけて演武をする武道です。私の修練する流派「伯耆流」の始祖片山伯耆守藤原久安は、「武は矛を止めるのではなく、矛が止むのである」を武道の理念としました。これは、武道の本質は戦いに打ち勝つことにあるのではなく、戦いを知ることで戦わずに済ませることにあるという、平和への願いです。この「矛止」の精神は、紛争を解決するための知識や経験を積み重ねることで将来の紛争を未然に防止するという、弁護士の果たすべき役割に通じると考えています。
居合道から学んだ「矛止」の精神をもって、お客様のサポートに誠心誠意尽力して参りたいと思っております。もとより未熟者でありますが、宜しく御指導、御鞭撻の程、お願い申し上げます。
人を裁く資格とは?
弁護士 遠山大輔
ついに裁判員裁判が始まりました。京都でも昨年10月に1件、12月に2件が実施されています。私も既に1件、国選弁護人として担当することが決まりました。
さて、マスメディアでは、裁判員となった市民の感想のほかに、裁判員が証人や被告人にどんな質問をしたかが詳しく報道されています。裁判員の発言の中には、質問ではなく、意見を述べたり、被告人を諭すものもあるようです。判決後に「声明」が発表されたケースもありました。このような裁判員の「発言」はどのような意味を持っているのでしょうか。
私は、人を裁く人は、裁かれる人によって「裁くことを許される」必要があると考えています。裁かれる人が「あなたに裁かれるなら本望だ」と感じなければ、その人に対する真の意味での裁きにはならないのです。裁判員の方々は、事件と被告人とを真剣に理解しようと努力された上で、意識するかどうかは別として、「裁くことを許されたい」と感じ、言葉をかけるかたちで、被告人に自分に対する理解を求めているのではないでしょうか。「声明」についても、事件と被告人とをよく理解した立場から、例えば被告人と社会とのつながりに一役買うかたちで、あるいは社会に問題提起するかたちで、事後的に「裁く資格」を確認しようとしている、私にはそう感じられます。もし、裁判員を体験されたら、是非感想をお聞かせ下さい。
裁判員裁判に関連してご報告しますが、共著「入門法廷戦略-戦略的法廷プレゼンテーションの理論と技術」を現代人文社から出版しました。刑事弁護活動一般の発展に少しでも寄与できればと願っています。
将来の備え
弁護士 拝野厚志
1.私は現在、京都弁護士会の高齢者障害者センター運営委員会のうちの財産管理部会に所属しています。同部会では高齢者の方の財産をめぐる法的問題や処理のあり方の検討等をしております。そのせいか、遺言や相続をめぐるトラブル、高齢者の方の財産管理の相談をよくお受けします。
2.遺言によって、お持ちの財産をどのように分配するかを予め明確にしておくことは後々のトラブルを防ぐことになります。また、財産管理についても、将来、財産を十分管理できなくなる場合に備えて、信頼できる方に将来の財産管理をお願いしておかれればご自身にとっても周りの方にとっても安心です。当事務所でも任意後見契約をはじめ、司法書士や税理士とも連携をとりながら、事務所全体できめ細かく財産管理のサポートをさせていただいておりますので、お気軽にご相談下さい。
3.今年は、高齢者虐待アドバイザー研修を受講することになっており、また、白浜所長とともに京都弁護士会の遺言相談センターの相談担当として登録させていただいております。今年も高齢者の方の法的サポートに力をいれていきたいと思っております。
弁護士の情報収集手段
弁護士 里内 友貴子(旧姓 細川)
早いもので、弁護士になって1年が経ちました。着任早々から、様々な事件を担当させていただきましたが、その中で特に思うことは、情報収集の難しさです。情報(証拠)が手元にないために不利な立場にたたされることは、本来あってはならないと思うのですが、「あの資料があればなぁ」と悔しく思うことが少なからずありました。
弁護士が証拠を集める手段のひとつに弁護士会照会制度があります。これは、弁護士会を通じた照会に対して回答を求めることで資料を収集する制度で、人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の職務の公共的性格に鑑みて、弁護士法によって認められています。裁判所による照会である調査嘱託や検察官による捜査関係事項照会と同趣旨の制度であり、公的機関である弁護士会から照会を受けた照会先は回答義務を負っています。しかし、照会先によっては、この制度を誤解され、回答を拒絶されることがあります。私は、京都弁護士会「弁護士法による照会」委員会に所属し、回答を拒絶したところへ、京都弁護士会として抗議申入を行う活動に参加しています。この活動によって、多くのところが回答に応じてきますので、弁護士会照会制度の実効性は高いものです。今後も、この活動を通じて、私達弁護士に対する皆様の期待に応えるべく、がんばろうと思っています。
ただ、もとより、証拠等資料をお持ちであれば、法的問題の解決が一層正確かつ円滑にすすむことは言うまでもありません。大事な取引等については、念のため、関係資料一式を保管されると共に、ご相談の際には是非それら全てをお持ちいただければと存じます。
支店の開設
事務長 田村 彰吾
このたび当所は、京都府長岡京市に一般の会社の支店にあたる従たる事務所を開設しました。法律事務所が支店というと違和感を感じられる方もおありかと思いますが、弁護士法の改正で法人化した弁護士事務所は支所を出すことが出来ることとなり、平成20年12月から法人化していた当所も、支所を開設する運びとなりました。
かねてより所長白浜は「身近な法律サービスの提供」を目指しており、また弁護士過疎偏在問題対策活動も積極的に行っていたところでしたので、今回の支所開設でまた一歩理想に近づいたものと自負しております。
支所設置にあたっては、たくさんの方のお世話になりました。中でも、支所開設で皆様にご不便をおかけすることがないよう主事務所との連携をとれるかについては、多くの方のお知恵とお力をお借りしました。もちろん、これからも改善に努めますが、現時点でも主従事務所の連携は業務に支障がないレベルまで整ったと確信しております。
当面の間は、支所に所長白浜も常駐し、地域密着の法律サービスの実現に邁進していきますが、本所では、私が事務長として、これまでのお客様と各弁護士とのスムースな橋渡しができるようにお手伝いをさせていただこうと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。