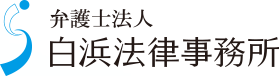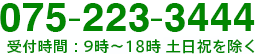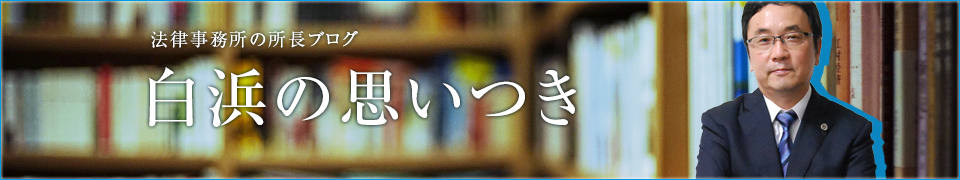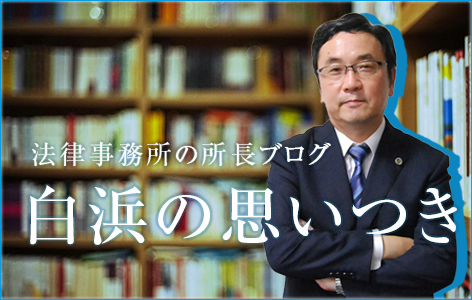2008/10/06
電子内容証明郵便は、欠陥商品?
電子内容証明郵便というシステムは、わざわざ郵便局にいかなくても内容証明郵便が発送できるので、便利です。このため、我々弁護士もよく使っています。しかし、この渋滞が頻繁に生じていることは意外と知られていません。実は、使用する時間によっては、28時間待ちとか、40時間待ちになってしまう事態が頻繁に生じています。
このため、私の事務所では、内容証明郵便については、急ぐ事件では電子内容証明郵便は使わないようにし、電子内容証明郵便を使うのは少し遅くなっても構わない事件に限ることにした上で、電子内容証明郵便を使うとしても必ず待ち時間を確認することを徹底するようにしています。「急がないようなら電子でもいいですか。」、「今、※※時間待ちですけど、郵便局走りますか。」というのは、うちの事務所の合い言葉になりつつあります。遅れる原因については公表されていないのでわかりませんが、郵政民営化となってもこのようなことでいいのかと思ってしまいます。他の企業が渋滞のない電子内容証明郵便を市場に送り出してくれたら、利用者が増えるのではないかと思います。
なお、このことを知らない弁護士も大勢いるのだろうと思います。事務的なことは、事務員さん任せにしてほったらかしという弁護士の方が多いというのが、この業界の実情だからです。でも、時効などが問題となる事例の場合、この郵便を使ってアウトということになってしまったら、完全な弁護過誤になると思います。この点は、年末年始など、郵便事情が悪いときの郵便物発送でも同じことなので、気をつけねばなりません。