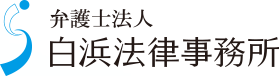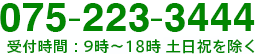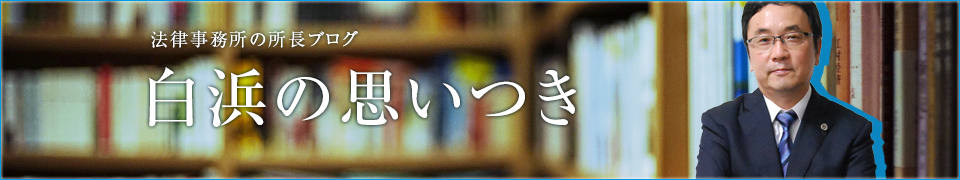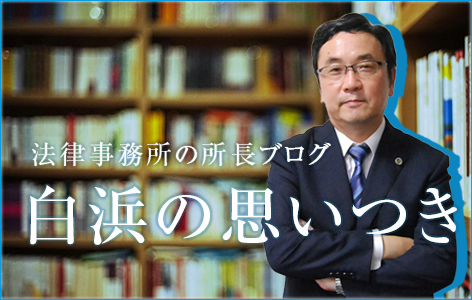2008/09/29
共立工機が注目されています
和議債権を完全履行したおそらく最後の企業となるであろうということで、私の事務所のホームページで紹介している共立工機が、日本一明るい経済新聞で取り上げられたそうです。
http://www.seiwabs.co.jp/akaruibn/keizai/sb_865.html
同社のすごいところは、然したるスポンサーもなく、誠意と熱意で再建に成功しているところです。なぜ、このことがすごいかがわかりにくいかも知れませんので、少し説明させてもらいます。通常の企業は、自己資金だけで資金繰が完全にできるところは少なくて、資金繰のためには金融機関から融資を得たりしながら経営しているわけですが、和議、今で言う民事再生をした場合には、金融機関からの融資が得られないため、資金繰を自社の売上管理だけで行わなければならなくなります。企業というものは、予想もしない資金需要が生じたりすることがありますし、ましてや再建中の企業の場合、色々な問題が生じやすいので、再建途中で資金ショートすることはよくあります。このため、スポンサーなしの再建は本当に難しいのです。私としては、そのようなスポンサーなしで再建に成功した共立工機はすごい企業だと思うわけです。
弁護士は、民事再生など、企業再建のための法的手続を支援しますが、いかに弁護士が法的な手続を提供したとしても、その企業自身が再建しようと努力しない限り、企業再生は困難です。共立工機についても、私は、和議という手続をしただけのことで、再建は、共立工機という企業体、つまり、社長を中心とした従業員の皆様の努力や取引先、債権者の皆様方のご協力があったからこそ、実現することができたわけです。このことも私が共立工機をすごい企業だと思う理由の一つです。
なお、経理等が不透明な企業が多い中、共立工機は、裁判所が関与して経理面が債権者等にオープンにされて、再建途中でも金融機関に全てを開示しながらやってきた企業ですから、金融機関からの信頼感は以前にも増して高まっています。和議の後、落ちた信用を回復するべく、地道に再建に努力した結果がようやく実を結んできたわけで、その結果を上記のように取り上げていただいていることは、本当に喜ばしいことだと思います。
私としても、共立工機の再建のような奇跡に携わることができたことは、本当にうれしいことだと思います。今後も、そんなお手伝いができたらと思って、民事再生などの企業再建の手続について、知識と経験を深めるべく、がんばっています。