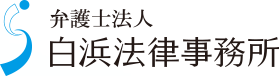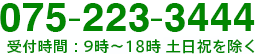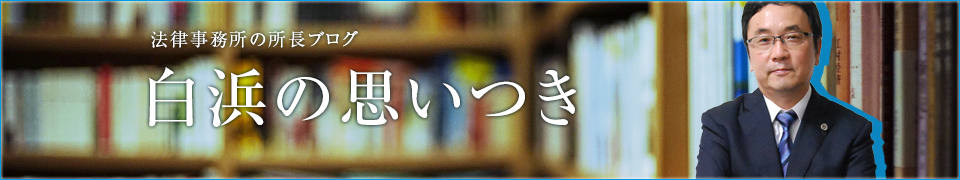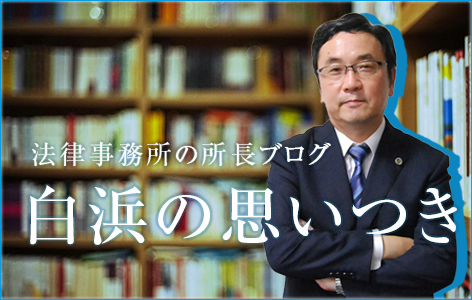2018/08/13
2018/04/06
司法試験の合格率を緩くしても志願者は戻らないのでは?
先日発表された読売新聞の論説では、法科大学院の入学者が減っている原因を司法試験の合格率の低さが主因のように述べておられるようです。しかし、これは、例えば日本全体としての大学の進学率が低くなったとして、その原因を大学全体としての合格率が低いからだと言っているようなものだと思います。法科大学院の希望者が減っているのは、司法試験が難しいからではなく、司法試験に合格してからの就職や将来の展望に問題があるという職業を得るための資格試験として致命的な問題が現に生じているからです。将来の展望が持てるのであれば、驚異的な合格率でも志望者は集まるというのは、旧司法試験で実証されていることです。
旧司法試験の問題点としては、志望者の割に合格者が少なく時間をかけて受験しても合格するかはわからないということが原因で優秀な人材が敬遠する傾向があるということが指摘されていて、法科大学院制度ができる際には司法試験の合格率は緩やかなものになるということが広く言われていました。しかし、法科大学院の卒業生の合格率が緩やかなものとなるには、法科大学院への入学の段階で厳しい選抜があることが前提となっていないと資格試験としてはおかしなことになります。現状は、法科大学院の選抜機能は低下している上に、今の司法試験は、旧司法試験の時代と比べるとはるかに多数の合格者がでるようなものとなっているにも関わらず、既にその受験の前提である法科大学院に志願者が集まらない状態になってしまっているのですから、司法試験の合格者を増やせば志願者が増えるということにはならないということは明らかだと思います。
司法試験の合格率が問題とされるべきは、法科大学院の間での入学希望者を自分の大学院に集めるための競争の中での指標としてのものだろうと思います。資格試験として一定の水準が必要な司法試験では全体としては相当な合格率があることがむしろ求められているはずです。要するに個々の法科大学院が、他校よりも合格率が向上するよう教育に努力するべきことなのです。有名大学の試験が難しいから易しくしてくれなどと世間にアピールするような高校はないのに、なぜ法科大学院の関係者だけが司法試験を易しくしろということを言われるのか不思議です。
何度も言いますが、法曹養成の仕組みの問題として試験の合格率を問題にすることはおかしいのです。法科大学院の関係者が、自らの学校の志願者が減少していることについて、司法試験の合格率が低いということを問題としていることがあったとしても、それはあなたがもっと努力しなさいよということであって、試験をもっと易しくしてやれなどと第三者がいうのは筋が違うのではないでしょうか。
2018/04/04
弁護士を自主的にやめる人が減ってきたようです
平成27年4月4日に60期以降の弁護士の人数をチェックしたときには大きな変動があったので、ブログにも書きましたが、同じように平成30年4月4日に人数チェックをしてみたところ、63期だけが突出して人数減となった他は、大きな変動はなく、弁護士をやめる人は減ってきたような印象を受けています。
具体的に言いますと、平成30年3月末と4月4日で人数に変動がなかったのが、60期(2,057人)と61期(2,060人)、62期(2,040人)です。急減したのが63期で1,836人が1,825人と11名の減です。微減が64期(1,880人が1,878人へ)と66期(1,775人が1,773人へ)、68期(1,556人が1,555人へ)、69期(1,574人が1,572人へ)です。逆に増えた期もあって、65期(1,824人が1,830人へ)と67期(1,722人が1,730人へ)、70期(1,378人が1,393人へ)が増えています。特に、70期は就職難が緩和されたと言われているように、裁判官や検察官の数から推計される最大可能値である1,431人からすると97.3%が弁護士となっていることとなり、他の期が達成したピーク比率にほぼ達したことになっています。
63期は、弁護士白書などから推計される最大人数が1,926人でしたので(私が実際に観測した最大人数は1,922人ですが。)、弁護士を自主的にやめた人がほぼ100人となったということになります。
63期ぐらいまでは、弁護士の仕事はいくらでもあるかのような話を信じて法科大学院に入学した人が多かったものが、65期ぐらいからは弁護士の就職環境が厳しいことが周知されてから法科大学院に入学した人が多くなっているものと私は推察しています。このように厳しいことがわかりながら法科大学院に入学した人は、弁護士になってからやめるという人は少なくなってきているということではないかなと思います。
もう少しでも司法試験合格者が減るということになれば、異常な供給過剰状態から脱して、弁護士の就職難も解消されることになるのかも知れません。ただ、合格者を減らすことは単年で実施するのではなく、しばらくは継続しなければならないということに注意が必要です。供給過剰時期に弁護士資格を得て今は弁護士ではないという人達が再度弁護士になるということができるということがあるからです。このことが、新人の就職状況に影響を与えて、資格試験としての魅力を落とし、志願者を減らすことになってしまうことは避ける必要があると私は思います。
2018/01/04
2018年新年のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。今年は、平成30年となりました。今年もよろしくお願い申し上げます。
年末に事務所のHPを一新しましたので、ブログのデザインが変わり、少しすっきりしたような感じになりました。肝心のアドレスも変わっていて、現時点では、検索してもみあたらなくなっているようです。誠に申し訳ございません。今、たどり着いてお読みいただいている方には感謝申し上げます。
ところで、私が、京都弁護士会の会長をしていた際には、個人的な発言がやりにくく、ブログの更新もあまりできませんでしたが、そのときの惰性なのか、昨年も、あまり更新ができておりませんでした。
このブログは、裁判制度の問題を指摘して、その改良を気楽に提案して、皆さんの反応をみてみようというところで始めたわけですが、期せずして、法曹養成制度の欠陥が露呈していく中、その政策転換のためのデータの提供ということを担うことになりました。この話題だけだと重苦しいところがあります。今年は、初心に返って、裁判制度や法制度の使いにくさとかその改善の提案なども書こうかなと思っています。
ところで、今年は、戌年です。京都は、寺社仏閣が沢山あるわけですが、子は大豊神社、亥は護王神社など、有名なところもある中、戌年にちなんだ神社を私はみつけることができませんでした。
昨年は、奥さんが探してくれた寺町鞍馬口の天寧寺の諌鼓鶏(かんこどり)を紹介しましたが、今年も奥さんが探してくれた鳴滝の三宝寺の子宝犬を紹介します。
三宝寺は、福王子の北、周山街道の入口近くにある名刹です。ペット霊園もあるようです。
これが子宝犬です。


灯籠には、なぜか小さいダルマが鎮座してます。


ここにも小さなダルマが並んでいます。


なお、三宝寺の正面は、こんな感じです。子宝犬は、奥の方にあります。

PS:狛犬というと、白浜事務所のご近所の下御霊神社(丸太町通の南に位置しながら上京区となっているらしい)の笑う狛犬も紹介しておきましょう。阿吽(あうん)の呼吸の語源とも言われるように、狛犬は、一方が口を開けているのですが、下御霊神社の狛犬はまるで笑っているようにみえるということで有名らしいです。京都の悪霊を鎮めるための役目を担っている神社ということですから、この笑い顔で悪霊を追い払うというところでしょうか。