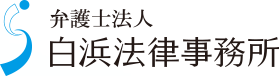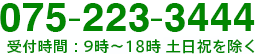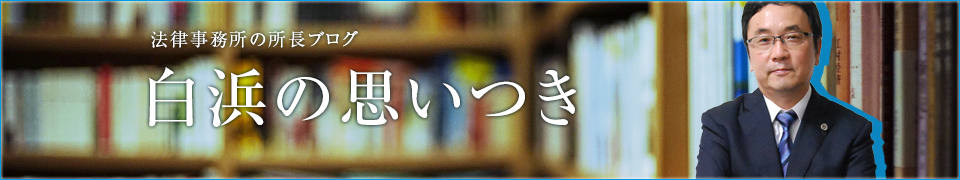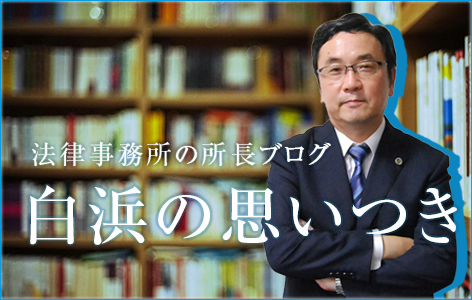2022/06/23
続:弁護士の人口増を司法書士と比較してみた
知り合いの司法書士の先生から、データをいただいたので、人数の推移について、弁護士白書のデータと比較してみた。
1990年における司法書士と弁護士の人口の比率を比較した場合、全体では、まだまだ司法書士の人数の方が多く、弁護士との比率は0.85となっていた。地域的な違いについて検討すると、司法書士の人数に比較して最も弁護士の数が少なかった地域は、島根県で0.12となっていた。続いて、鹿児島県の0.15、岩手県0.16、鳥取県0.17、宮崎県0.17、三重県0.18、山口県0.18、福島県0.19ということになっていた。これに対し、弁護士の数が多かった地域は、1位が東京都で12.26と弁護士の数が圧倒的に多く、その次が大阪府で1.42となっていて、他の道府県は全て弁護士の数の方が少なかったことになっていた。大阪府の次が愛知県で0.99、神奈川県0.98、沖縄県0.93、札幌0.83、京都府0.76、福岡県0.73となっていた。この具体的な数字は、以下のPDFのとおりである。
これが2000年になるとどうなるかというと、弁護士人口が急増した結果、全体では、弁護士の人数が司法書士より多くなり、司法書士との比率は1.07となった。地域的な違いについて検討すると、司法書士の人数に比較して最も弁護士の数が少なかった地域は、この時点でも島根県が1位で0.13となっていた。続いて、鳥取県の0.19、岩手県0.23、釧路0.23、鹿児島県0.24、岐阜県0.25、山口県0.25、山形県0.25ということになっていた。これに対し、弁護士の数が多かった地域は、1位が東京都で13.82と弁護士の数が圧倒的に多く、その次が大阪府で1.60、神奈川県1.16、愛知県1.09となっていて、他の道府県は全て弁護士の数の方が少なかったことになっていた。愛知県の次が札幌で0.94、福岡県0.85、京都府0.83、沖縄県0.82となっていた。この具体的な数字は、以下のPDFのとおりである。
2010年について、同じ検討をすると、弁護士人口の急増が続いた結果、全体としての人数の差は大きく拡大し、弁護士と司法書士の人口比率は1.45となった。地域的な違いについて検討すると、司法書士の人数に比較して最も弁護士の数が少なかった地域は、1位は岐阜県で0.37、続いて、島根県の0.42、山形県0.42、鹿児島県0.44、長野県0.45、三重県0.47、富山県0.47、滋賀県0.49、鳥取県0.50、福島県0.50ということになっていた。これに対し、弁護士の数が多かった地域は、1位が東京都で15.26と弁護士の数が圧倒的に多く、その次が大阪府で1.66、札幌1.30、神奈川県1.24、愛知県1.23、仙台1.15、福岡県1.04、沖縄県1.03となっており、他の地域では、まだまだ司法書士の数が多くなっており、次の京都府が0.95となっていた。この具体的な数字は、以下のPDFのとおりである。
2022年については、前回のブログで整理したとおりで、弁護士人口の急増が続いた結果、弁護士と司法書士の人口比率は1.92と弁護士の数がほぼ2倍となっている。地域的な違いについて検討すると、司法書士の人数に比較して最も弁護士の数が少なかった地域は、1位は徳島県で0.63、続いて、岐阜県の0.65、山形県0.67、愛媛県0.67、滋賀県0.69、秋田県0.69、鹿児島県0.71、長野県0.73、福島県0.74となり、1990年には1位だった島根県は0.79で鳥取県も0.78と山陰地方での弁護士と司法書士の比率が相対的に小さくなっていることが示されている。後述する司法書士人口の推移表によれば、函館は、2010年から2022年にかけて司法書士の人口が最も減少した地域となり、鳥取県と島根県がこれに続いている。山陰地方でも弁護士と司法書士の比率が相対的に小さくなったのは、司法書士の人口が減ったことも原因となっているものと思われる。徳島県が1位となったのは、全国的にみて、2010年から2022年にかけての弁護士の増加率が最も低かったためと思われる。愛媛県が上位に急上昇したのも同様の理由と思われる。これも後述する弁護士人口の推移表を参考としていただきたい。これに対し、弁護士の数が多かった地域は、1位が東京都で17.44と比率差はさらに拡大している。その次も変わらず大阪府で1.98、札幌1.63、愛知県1.59、仙台1.48、京都府1.43、函館1.43となったが、神奈川県は1.42で福岡県でも1.41と比率差の拡大が他の都市部よりも小さくなっている。神奈川県は、司法書士の人口増加率が東京都に次ぐ2位となっていることが影響しているものと思われる。これも後述する司法書士人口の推移表を参考にしていただきたい。ちなみに、2022年の具体的な数字は、既に公表済ではあるが、以下のとおり、若干の誤字等の修正を加えている。
司法書士の人数について、弁護士の側で整理したものはあまりなかったので、今回の分析で私が驚いたのは、司法書士も、都市部では増えているが、人口過疎地では減少傾向があるということである。2010年と2022年を比較して最も減少しているのが函館で0.75、次が鳥取県で0.82、島根県0.83、富山県0.86、秋田県0.87、福井県0.88、岩手県0.88、青森県0.90となっている。山陰や東北、北陸地方での減少は顕著と言える。この詳細は、以下のPDFのとおりである。
なお、弁護士人口の増加を増加比率だけで考えた場合、2010年から2022年との比較で最も増えているのは、埼玉県で1.76、次が千葉県1.76、茨城県1.71、京都府1.71、鹿児島県1.71ということになっている。東京都は、全国の増加率平均の3.19から少し大きい程度の3.40に過ぎない。大阪府は、意外にも、最近では弁護士人口の増加率が小さい地域となっており、2000年と2010年との比較では4番目、2010年と2022年との比較でも11番目となっている。弁護士の人口の変化につき、増加率を加味して、整理したものが、以下のPDFである。修習生が就職する法律事務所を決めるときや、若手弁護士が独立してどの地域で弁護士をするかを決める際の参考としていただければ幸いである。これらのデータは、修習生が就職する法律事務所を決めるときや、若手弁護士が独立してどの地域で弁護士をするかを決める際の参考となるかも知れない。