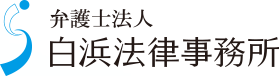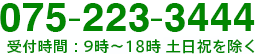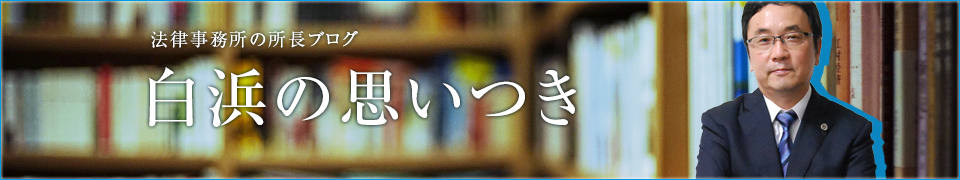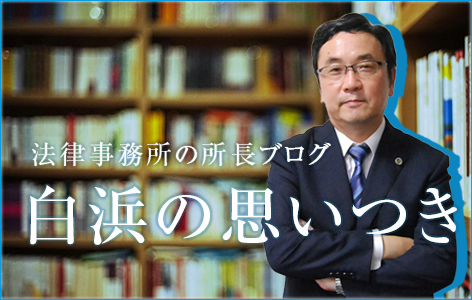2019/09/10
ゴルフ練習場に関する建築規制や営業規制には抜本的改正が必要では?
千葉では、ゴルフ練習場が倒壊して、周辺の住宅地に甚大な被害が生じているということである。被害者の皆様の窮状には察するに余りあるところがある。
昔、住宅地に近接したゴルフ練習場によるボールの飛来や照明光の照射被害の事件に関わったことがある経験からすると、ゴルフ練習場に関する建築規制や営業規制には大きな問題があるように思う。
現時点の法令を細かに検討したわけではないが、そもそもゴルフ練習場が住宅地に建築できるようになっていること自体が間違いと言わざるを得ない。騒音や光の問題が生じて、近隣住民にとって迷惑だからである。練習場からすれば住民の利用があって営業上は有利なのかも知れないが、住宅地でなくても営業は可能なのだから、住宅地への建築を許可する必要性はそもそも存在しない。また、鉄塔に関しては、ネットを張った状態で強い台風による風速にも耐えられるような強度を必要とするように規制しなければならないし、台風などに備えて、ネットを下げることができるような構造のものでなければ、建築を認めないようにするべきである。強い風が予想される場合には、ネットを下げて営業を中止するような営業規制も強化するべきである。これは安全上当然のことである。また、仮に鉄塔が倒れた場合に、住宅地や鉄道、主要道路などに到達するような高さの鉄塔はそもそも建築を許可するべきではない。これも周辺の安全上当然のことである。
ところが、現状では、危険なゴルフ練習場は各地に存在している。少なくとも、鉄塔の強度や可動式ネットへの切換と営業規制の強化は、現時点で法令がそのような規制となっていないのであれば、現行の練習場にも強制するよう法令が改正されるべきであろう。