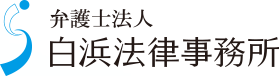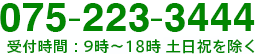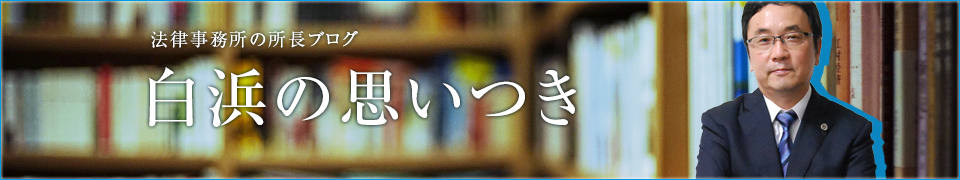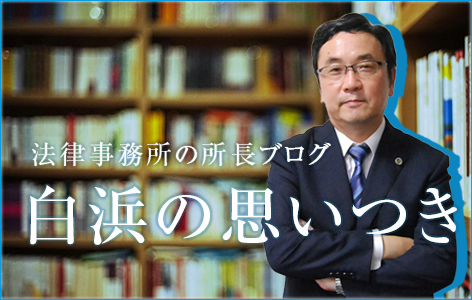2021/09/24
弁護士人口のシミュレーションと現実とはどう違っているのだろうか
Back to the Future Part IIは、1989年発表の映画で、この映画では2015年の未来にタイムトラベルしていたのですが、我々は、既に2021年を過ごしているわけで、映画が予想していた未来を通り越してしまっていることになります。1989年の時点で予想された未来は、今の我々が住んでいる世界とはかなり異なっていましたね。未来予想は難しいことなんだなと思います。
ところで、私が「司法試験に合格しても弁護士になれるとは限らない」とブログに書き込んだのが、2005年のことなのですが、このときに指摘していた就職難は、私の予想をはるかに超えて厳しいものとなりました。ただ、2018年頃より、司法試験合格者の就職難は大きく改善され、現在では、弁護士人口が増えない県が発生するという新たなゼロワン問題が生じるようになっているなど、弁護士人口をめぐる問題は我々の予想できないような変化を始めているように思えます。
結局のところ、貸与制の最後のあたりの66期ぐらいの方々が一番大変だったように思います。この方々が弁護士として頑張ったことが、結果的に新しい期の方々の就職難の解消につながっているのかも知れません。いわゆる谷間世代への支援は、この観点からも重要なことと思います。この苦難の時代から、今の就職状況にどのような経過で変化していったのかということは、色眼鏡をかけずに、冷静に分析する必要があるように思います。
別添のPDFは、弁護士白書に掲載された弁護士人口に関するシミュレーションを整理したものです。合格者が3000人となることが前提となっていたり、新規法曹が2000人ということが前提となっていたりするなど、その当時問題となっていたことが反映されているわけですが、シミュレーションよりは実際の弁護士人口の増員は少なくなっているようには感じます。なお、2011年から2014年までは新規法曹が2000人であったり1500人であったりした場合のシミュレーションも掲載されていますが、比較の意味では実際に近かったものだけを取り上げています。また、弁護士人口はいずれも3月31日現在のものが弁護士白書では示されています。2021年の3月31日現在の弁護士総数は私には確認できていませんので、現時点(9月24日)の日弁連HPからの検索結果が43,084人だったので、これを便宜上入力しています。
ただ、いずれにしても、我々弁護士は実験用動物ではないので、実験のような人口政策に踊らされる理由はありません。そうならないためには、実態、この問題については、就職難の現状とか、弁護士人口の増加がない弁護士会と増えている弁護士会との比較などのデータを整理して、立法事実として示すことが求められています。少なくとも、5年以上前の感覚で意見を述べるということでは立法事実とは乖離した主張となることに注意が必要です。かかる意味でも、過去のシミュレーションがどうだったのかということを振り返ってみることにも意味があるかなと思って整理した次第です。